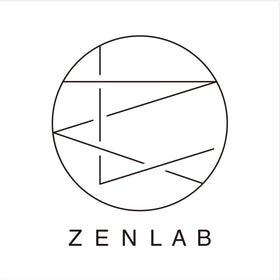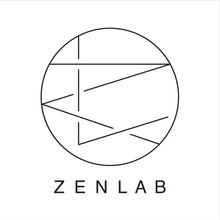夏を惜しみ、秋を迎える小さな工夫
お盆を過ぎると、日差しの強さはまだ残りながらも、どこか秋の気配が漂い始めます。朝夕に吹く風が少し柔らかくなり、庭先では蝉の声に混じって、鈴虫やコオロギの音色が聴こえるようになると、「季節が確かに動いているのだ」と感じさせられます。暮らしの中にこの移ろいを取り入れることで、日常はより豊かでしなやかなものになっていきます。
夏を惜しむ心と、秋を迎える喜び。その両方を大切にできるのが、この時季ならではの楽しみです。たとえば茶室や居間のしつらえでは、真夏に用いた硝子の茶入れや茶碗から、少しずつ温かみを感じさせる器に移していくと、自然に秋の気配が漂います。窓辺に掛けた風鈴を外し、障子越しに秋の光を楽しむのもよいでしょう。夏の強い日差しから、秋のやわらかな西日へと移る光の変化は、部屋の雰囲気を一変させてくれます。
 食卓においても、季節の移ろいは手軽に取り入れることができます。盛夏には冷たい麦茶や氷を浮かべた冷煎茶が欠かせませんが、初秋にはほうじ茶や番茶の湯気が心地よく感じられるようになります。果物も、スイカや桃から、梨や葡萄、栗へと変わっていきます。器や盛り付けにひと工夫を添えれば、日常の食卓が小さな歳時記の舞台に変わります。
食卓においても、季節の移ろいは手軽に取り入れることができます。盛夏には冷たい麦茶や氷を浮かべた冷煎茶が欠かせませんが、初秋にはほうじ茶や番茶の湯気が心地よく感じられるようになります。果物も、スイカや桃から、梨や葡萄、栗へと変わっていきます。器や盛り付けにひと工夫を添えれば、日常の食卓が小さな歳時記の舞台に変わります。
 たとえば、お茶席でいただく和菓子もまた、季節の入り口を彩る大切な存在です。写真の菓子は「着せ綿(きせわた)」と呼ばれるもので、旧暦の重陽の節句(九月九日)に、菊の花に真綿をかぶせて夜露を含ませたという風習を表しています。淡い桃色の菊のかたちに、白くふわりと重ねられた綿が添えられた意匠は、夏の名残と秋の気配を繊細に映し出しています。甘味をいただきながら、季節の詩を口に含むようなひとときとなるでしょう。
たとえば、お茶席でいただく和菓子もまた、季節の入り口を彩る大切な存在です。写真の菓子は「着せ綿(きせわた)」と呼ばれるもので、旧暦の重陽の節句(九月九日)に、菊の花に真綿をかぶせて夜露を含ませたという風習を表しています。淡い桃色の菊のかたちに、白くふわりと重ねられた綿が添えられた意匠は、夏の名残と秋の気配を繊細に映し出しています。甘味をいただきながら、季節の詩を口に含むようなひとときとなるでしょう。
衣服の選び方も、季節を感じる大切な要素です。真夏に活躍した薄手の麻やリネンから、柔らかい木綿や軽やかなウールへと少しずつ移し替えていくと、体も心も季節に馴染んでいきます。まだ昼間は暑さが残るため、完全な衣替えではなく「重ね方や小物で工夫する」ことが、この時期ならではの知恵といえるでしょう。
さらに、暮らしに香りを添えるのもおすすめです。夏には涼を呼ぶ白檀や薄荷の香りが心地よく感じられますが、秋が近づくと、菊や萩を思わせる落ち着いた香りや、やや深みのある香木が似合います。焚きしめるお香やアロマオイルを変えるだけで、室内の空気がふわりと秋めいていきます。
 こうした小さな工夫は、決して大げさなものである必要はありません。花一輪を入れ替える、器をひとつ変える、窓から入る風を感じながらお茶を淹れる──そうしたささやかな所作が、暮らしに四季を運び込みます。そしてその積み重ねが、夏を惜しみながらも、次の季節を迎える心を整えてくれるのです。
こうした小さな工夫は、決して大げさなものである必要はありません。花一輪を入れ替える、器をひとつ変える、窓から入る風を感じながらお茶を淹れる──そうしたささやかな所作が、暮らしに四季を運び込みます。そしてその積み重ねが、夏を惜しみながらも、次の季節を迎える心を整えてくれるのです。
季節の移ろいを敏感に感じ取ることは、日本の暮らしに古くから根付いてきた美意識でもあります。夏と秋が交差する今だからこそ、五感をひらいて身近な変化を楽しみたいものです。