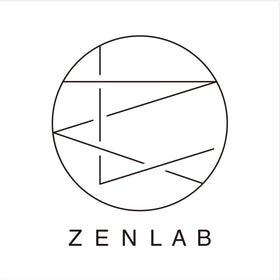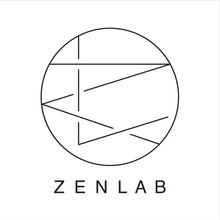静けさを編む— 花籠のかたちに見る、美とこころ —
茶室にそっと置かれた花籠。
その存在はひかえめながらも、ふとした瞬間に視線を引き寄せ、そこにある空気をやわらかく変えていきます。
竹のしなやかな曲線と、編み目に込められた手の記憶。
花を生けるためのこの小さな器には、自然と調和する美しさ、そして季節と心をつなぐ静けさが宿っています。
茶の湯の席において、花は主役ではありません。
けれども、その佇まいひとつで、室内の空気がふっと変わる——
花を受けとめる「花入」は、静かな存在感をもって、時に茶席全体の印象を導いてくれます。
とりわけ、竹で編まれた花籠には、手仕事のぬくもりとともに、自然へのまなざしが込められています。
素朴で、どこかいのちを感じさせる竹籠。そこには、形や編み方に物語があり、ただの器ではない、何か深いものが宿っているように思うのです。
たとえば、網代(あじろ)花籠。
細く割った竹や樹皮を、交互に規則正しく編み込んだもの。網代とはもともと、川に仕掛ける漁具に由来する言葉で、その技法は古くから生活のなかで受け継がれてきました。
網代編みの美しさは、まさに「均整の美」。
整った格子が生む影と光のリズムが、茶室の静けさのなかでやさしく浮かび上がります。
その端正さのなかに、少しだけ花が乱れるとき、季節の移ろいがふと胸に沁みてくるのです。
 一方で、ふっくらと丸みを帯びた繭籠(まゆかご)は、また別の魅力を持ちます。
一方で、ふっくらと丸みを帯びた繭籠(まゆかご)は、また別の魅力を持ちます。
その名のとおり、蚕が紡ぐ「繭」のかたちを模してつくられたもの。
繭は春から初夏、蚕が桑の葉を食みつつ成長し、梅雨前に自らの糸でつくる命の住処です。
ふくらみのあるその形には、どこか母性や包容力を感じさせるやさしさがあります。
繭籠に一輪の花を生けると、どこか時間がふわりと緩みます。
人の手によって生まれたかたちのなかに、自然の循環がしずかに息づいている——
そんな感覚が、花とともに漂ってくるのです。
花籠に用いられる竹も、成長が早く、しなやかで強い素材。
水を吸えば表情を変え、乾けば軽くなる。そうした自然素材の呼吸に寄り添いながらつくられる器は、使い手によって生かされてはじめて完成するものなのかもしれません。