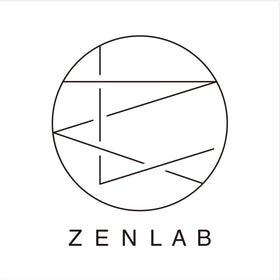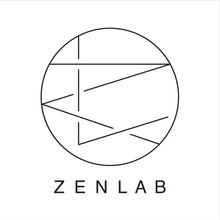梅雨の終わりを迎える六月下旬。あれほど鮮やかだった紫陽花の花も、日を追うごとに色を落ち着かせていきます。青や紅の花弁がくすみ、やがて乾いた紙のような質感に——。けれどその姿には、盛りを過ぎたものだけがもつ風情があり、時間の重なりが静かに滲んでいます。

床の間に、名残の紫陽花を一輪。竹籠の花入に、少しうつむきがちに生ければ、茶室の空気はがらりと変わります。華やかさはなくとも、静かな美しさがただよい、一服のお茶の時間に、深い余韻と静寂を添えてくれます。
六月の晦日には、「夏越の祓(なごしのはらえ)」という古来の神事が営まれます。茅の輪をくぐり、半年の穢れを祓って、残る半年の無病息災を願う——日本人が昔から大切にしてきた、折り目正しい季節のしきたりです。

この日にいただく和菓子に「水無月(みなづき)」があります。三角に切られたういろうに、小豆がのせられたお菓子。三角の形は氷を表し、小豆には邪気を祓う力があるとされます。かつて氷が貴重だった時代、暑気を払う願いを込めて氷のかわりに水無月を食べたといわれます。しっとりとしたういろうの食感に、小豆の優しい甘み。口に含めば、梅雨の湿気のなかに、ほのかな清涼が立ち上ります。

茶の湯においても、「祓い」のこころは通じています。茶道具を清め、花を整え、水屋を調え、床を拭く。これらすべては、客を迎える準備であると同時に、自身のこころを清めていく過程でもあります。
紫陽花の名残と、夏越の祓、そして水無月。すべてが「うつろい」と「清め」に通じるものです。盛りを過ぎた花にそっと手を合わせるように一輪を生け、静かに水無月をいただきながら一服をすすめる。言葉にしなくとも、そこには夏を迎える祈りが、確かに息づいています。
今年も、無事にここまで来られたことに感謝を。これからの半年も、健やかに過ごせますように——。名残の花と、静かな設えに、その思いを込めて。