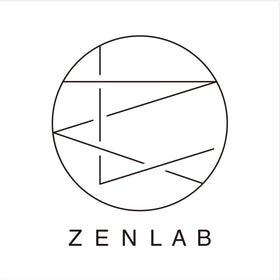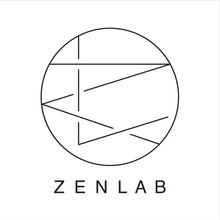風薫る五月、新緑がまぶしく、野の草花も一斉に勢いを増してきました。春の名残を背に、初夏のきざしを感じるこの時季、茶の湯では「初風炉(しょぶろ)」の季節を迎えます。
「初風炉」とは、風炉の使用を再開する最初の点前のこと。冬から春にかけて使っていた炉(ろ)を閉じ、風炉(ふろ)に切り替える節目のときです。茶の湯の一年は、十一月の炉開きに始まり、五月の初風炉で“夏の点前”へと季節が移っていきます。
この切り替えにより、茶室の景色や道具の取り合わせも一変します。畳に埋め込まれた炉を閉じ、床上に据え置かれた風炉へ。茶室には、軽やかさと涼やかさが漂いはじめます。

朱雀軒では、初風炉の点前に「面取り風炉(めんとりぶろ)」を用います。これは、風炉の口縁(こうえん)——つまり上端の角を斜めに削り取った形状の風炉で、鋭利な角をやわらげる「面取り」という加工に由来しています。
この面取りによって、釜と風炉のあいだから、わずかに炭火の赤みがのぞく——この「火の見える景色」が、面取り風炉の最大の魅力です。

一方、「切り合わせ風炉」は、釜の羽と風炉の口がぴったりと合わさっており、炭火が外からは見えません。見た目にはすっきりと端正な印象がありますが、火の気配は完全に隠されてしまいます。
初風炉のころは、まだ朝夕に涼しさの残る季節です。真夏のような暑さにはならず、茶室にわずかな温もりがあることが、むしろ心地よく感じられる時期。だからこそ、炭火の存在がほんのりと感じられる面取り風炉が、もてなしとしてふさわしいと考えています。
「見えない」ものを大切にするのが茶の湯の美学ですが、その「見えなさ」の中に、かすかに光る炭火を宿すことで、亭主の心づかいがそっとにじむ——面取り風炉には、そんなぬくもりがあるように思います。
また、面取り風炉のやわらかな曲線は、釜の姿を引き立て、風炉と釜のあいだに生まれるわずかな空間が、茶室の空気の流れすらも可視化してくれるようです。
五月、風炉のはじまり。緑の風が通り抜ける茶室で、湯のたつ気配に耳を澄ませ、火のぬくもりに心を寄せながら、一服のお茶を点てる。その静けさとやさしさこそが、初風炉のよろこびなのです。