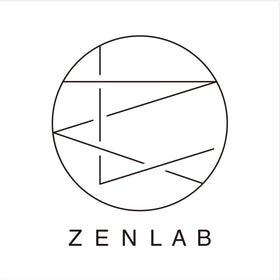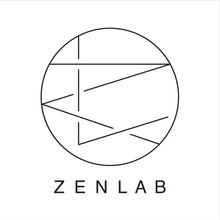二月は「如月(きさらぎ)」とも呼ばれ、暦の上では立春を迎える季節です。立春と聞くと春の訪れを感じさせますが、実際には一年で最も寒さが厳しい時期でもあります。風にまだ冬の冷たさが残り、朝晩の冷え込みも厳しく、雪が降る日も珍しくありません。しかし、そんな寒さの中にも、ふとした瞬間に春の兆しを感じることがあります。

茶の湯の世界では、季節の移り変わりを道具や設えを通して表現します。この時期、寒さをしのぐ工夫として用いられるのが「筒茶碗」です。筒茶碗は、口径が小さく、深さのある筒状の形をしており、茶碗の中の湯が冷めにくいという特徴があります。冷え込む冬の朝に、この茶碗で点てられた抹茶を口にすると、湯気が立ち上る温かさが身体にじんわりと染みわたります。
筒茶碗は、その形状だけでなく、釉薬の色合いや質感によっても季節の風情を映し出します。たとえば、深い瑠璃色や黒釉の茶碗は、冬の夜空や凍てつく大地を思わせます。一方、白釉や粉引の茶碗は、雪景色の静けさを表現しているようにも見えます。こうした茶碗を手に取ると、寒さの中で迎える春への期待が、静かに心に広がっていくのを感じることでしょう。

床の間の掛け軸や茶花も、春を待つ趣を大切にします。「弄花香満衣(花を弄すれば、香り衣に満つ)」という言葉が書かれた掛け軸が掛けられることもあります。これは、花を手に取れば、その香りが衣に満ちる、という意味で、春の訪れを感じさせます。茶室にこの掛け軸がかかると、一気に春がもうそこまで来ているようで、温かな風が待ち遠しくなります。

茶室の限られた空間に生けられた一輪の椿は、寒さに耐えながら春を待つ姿を映し出し、見る人の心に深く刻まれます。特に、開花直前のふくらんだ蕾は、生命の息吹を感じさせ、その控えめな美しさが茶席の趣と調和します。
一般的な生花では、開花した花を豪華に生けることが多いですが、茶席では蕾を用いることで、楚々とした美意識を表現します。蕾の椿は、開花したものよりも生き生きとしたエネルギーを孕んでいるとされ、その姿は茶室の静けさと相まって、凛とした雰囲気を生み出します。
二月の茶の湯は、まだ寒さが厳しい中で、春の気配を見つけ、感じ取る時間とも言えます。筒茶碗に手を添え、その温もりを感じながら、目の前の景色にふと春の兆しを見出す——そんなひとときこそが、この季節ならではの茶の湯の魅力ではないでしょうか。
寒さの中でこそ、温かいお茶のありがたみが身にしみます。そして、そこに込められた季節の趣を感じることで、冬から春への移ろいを、より深く味わうことができるのです。